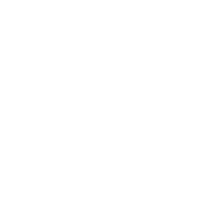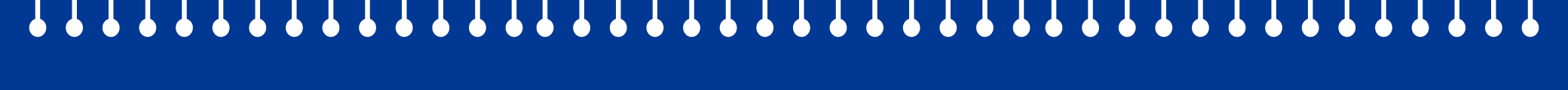
「ホームヘルパー」と「訪問介護」の特徴と違いは?介護のプロが教えるサービス内容と賢い使い方

「ホームヘルパー」と「訪問介護」。
似たような意味を持つこの言葉に、迷ったり悩んだりする方も少なくありません。
実は「訪問介護」はご自宅で受けられる”介護サービスの名前”で「ホームヘルパー」は”そのサービスを提供する専門スタッフ(人)”のことです。
この記事では、二つの言葉の違いはもちろん、それぞれの特徴や具体的なサービス内容、賢い利用法まで解説します。あなたとご家族が安心して暮らせるサービス選びの参考にしてくださいね。
目次
ホームヘルパーと訪問介護の基本的な違い

「ホームヘルパー」は人(職業・資格)を指し、「訪問介護」はサービス(制度)を指します。
| 比較項目 | 訪問介護 | ホームヘルパー(訪問介護員) |
|---|---|---|
| 分類 | 介護サービスの名称(形のないもの) | 専門スタッフの職種名(人) |
| 役割・内容 | 身体介護、生活援助などのサービスの総称 | 計画に基づき、左記サービスを実際に提供する |
| 目的 | 利用者の自宅での生活を支援すること | 利用者の心身の状況に応じて適切なケアを提供すること |
「訪問介護」というサービスの中に、「ホームヘルパー」という担い手が存在していると整理すると分かりやすいでしょう。
訪問介護とは
訪問介護は、介護保険制度に基づくサービスの名前です。目的は、利用者が住み慣れた自宅で可能な限り自立した生活を送れるよう支援することです。
これは介護保険法という法律で定められた公的なサービスで、全国どこでも同じ基準でサービスを受けられます。
訪問介護の利用には、要介護認定が必要です。市区町村に申請し、介護認定調査員による訪問調査や医師の主治医意見書をもとに、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者の状況に応じてケアプランを作成し、そのプランに沿ってホームヘルパーがサービスを提供する仕組みです。
ホームヘルパー(訪問介護員)とは
ホームヘルパーは、介護が必要な方のお宅を訪問する職業の人のことです。正式名称は「訪問介護員」と呼ばれており、これが法律上の正しい呼び方になります。
ホームヘルパーになるためには、介護職員初任者研修などの資格が必要です。具体的には、130時間のカリキュラムを受講し、修了試験に合格する必要があります。
役割は利用者の自宅を訪問し、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成したケアプランに沿って身体介護や生活援助を行うこと。一人ひとりの状況に合わせて、食事の介助から掃除まで幅広いサポートを提供する専門職です。
ホームヘルパーは具体的に何をしてくれる?仕事内容を解説

訪問介護のサービス内容は、主に3つに分けられます。
- 身体介護:食事や入浴など、直接体に触れるケア
- 生活援助:掃除や洗濯など、日常生活のサポート
- 通院等乗降介助:病院への付き添いをサポート
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①身体介護:食事や入浴など、直接体に触れるケア
身体介護は、利用者の体に直接触れて行うケアのことです。具体的には以下のようなサービスが含まれます。
<主な身体介護の内容>
- 食事介助:食べ物を口に運んだり、飲み込みやすいように刻んだりするお手伝い
- 入浴介助:浴室での体を洗う介助や、着替えのサポート
- 排泄介助:トイレでの介助やおむつ交換
- 着替えの手伝い:衣服の着脱や季節に応じた服装の選択
- 体位変換:床ずれ防止のために体の向きを変える介助
- 移動・移乗介助:ベッドから車椅子への移動など
身体介護は、体の自由が利かなくなった方や、筋力が低下した高齢者の方が主な対象となります。例えば、脳梗塞の後遺症で片麻痺がある方や、関節の痛みで自分では入浴が困難な方などが利用されています。
②生活援助:掃除や洗濯など、日常生活のサポート
生活援助は、日常生活を送るために必要な家事を代行するサービスです。
ただし、あくまで「利用者本人」のための援助に限定されており、家族のための家事は対象外となります。
<主な生活援助の内容>
- 掃除:居室、台所、浴室、トイレの清掃
- 洗濯:衣類の洗濯、干し方、たたみ方
- 調理:栄養バランスを考えた食事の準備
- 買い物代行:食材や日用品の購入
- 薬の受け取り:処方薬の薬局での受け取り
- ゴミ出し:分別してゴミ収集場所への運搬
例えば、関節痛などで積極的に動けない1人暮らしの利用者さんに代わって、掃除全般を依頼するといった使い方ができます。
このように、手が回らない部分をサポートしてもらえるのが生活援助の特徴です。
③通院等乗降介助:病院への付き添いをサポート
通院等乗降介助は、病院や薬局への通院時に必要な移動の介助を行うサービスです。介護タクシーなどの専用車両を使って、安全に移動できるようサポートします。
<通院等乗降介助の具体的な内容>
- 自宅から車両への移動介助
- 車椅子から車のシートへの移乗介助
- 病院での受付手続きの付き添い
- 診察室への移動サポート
- 会計手続きの手伝い
- 処方薬の受け取り同行
このサービスは、一人では公共交通機関を利用するのが困難な方や、車椅子を使用している方にとって欠かせないサービスです。家族が仕事で付き添えない場合でも、安心して通院することができます。
ただし、通院時の付き添いが介護保険適用の対象になる為には、ケアマネジャー(介護支援専門員)に介助が必要と判断してもらい、ケアプランに記載してもらう必要があります。また、自宅から病院までの往復の介助までしかサービスをお願いすることができません。病院内の介助は介護保険の対象外となります。
公的な「訪問介護」を賢く利用するために知っておきたいこと

訪問介護は介護保険を使った公的なサービスのため、利用するにはいくつかのルールや手順があります。これらを知っておくことで、よりスムーズに、そして賢くサービスを活用できます。
介護保険の訪問介護で「できること」と「できないこと」
| できること | できないこと |
|---|---|
| ・利用者本人の身体介護(食事、入浴、排泄など) ・利用者本人のための生活援助(掃除、洗濯、調理など) ・通院時の乗降介助服薬の声かけや見守り利用者本人が使用する居室や台所などの掃除 | ・利用者本人以外のための家事(家族の分の食事作り、来客への対応) ・日常の範囲を超える行為(大掃除、庭の草むしり、ペットの世話、車の洗車) ・医療行為(インスリン注射、たんの吸引など)金銭管理(通帳の管理、現金の出し入れ) ・趣味の付き添いや話し相手といった、直接的な介護に当たらないもの病院内の付き添い介助 |
公的サービスだからこそ、公平性を保つために厳密なルールが設けられています。
しかし、暮らしの中の「ちょっとした困りごと」は、こうしたルールの外にこそ多いものです。そんなときには、介護保険以外のサービスを検討することも選択肢の一つになります。
訪問介護の料金はどのくらい?自己負担の仕組みを解説
訪問介護は介護保険が適用されるため、利用者が支払う費用は全額ではありません。料金の仕組みを詳しく見てみましょう。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 料金の決まり方 | 訪問介護の料金は、「サービスの種類」と「利用時間」によって決まります。 身体介護の方が生活援助よりも料金が高く設定されており、時間が長くなるほど費用も増加します。 |
| 自己負担割合 | 利用者は、サービス費用の1〜3割を自己負担します。 この割合は所得によって決まり、一般的な所得の方は1割負担となっています。 |
| 料金イメージ | 身体介護30分の場合:約400円(自己負担1割の方) 生活援助45分の場合:約200円(自己負担1割の方) 通院等乗降介助:約100円(自己負担1割の方) |
ただし、これらの料金は目安であり、実際の自己負担額は、自己負担割合、要介護度、地域、事業所によって異なります。
また、要介護度に応じて月の利用限度額が設定されているため、その範囲内での利用が原則となります。
一方で、自費サービスは全額自己負担となりますが、その分サービス内容に制限がないという特徴があります。
訪問介護を利用するまでの流れ【4ステップ】
実際に訪問介護を利用するための手順を、4つのステップで解説します。
<ステップ1>
要介護認定の申請まず、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で要介護認定の申請を行います。
申請書と介護保険被保険者証、マイナンバーが分かるものを持参しましょう。申請後、介護認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況を調査します。
<ステップ2>ケアプランの作成
要介護認定が下りたら、ケアマネジャー(介護支援専門員)を選び、ケアプランを作成してもらいます。
ケアプランは、どのようなサービスをどのくらい利用するかを決める計画書です。利用者や家族の希望を聞きながら、最適なプランを一緒に考えてくれます。
<ステップ3>訪問介護事業所との契約
ケアプランに基づいて、訪問介護事業所を選び契約します。
複数の事業所を比較検討し、サービス内容や料金、スタッフの対応などを確認して選ぶことが大切です。
<ステップ4>サービスの開始
契約が完了すると、いよいよサービスが開始となります。
初回は事業所の責任者が同行し、サービス内容の確認や利用者との顔合わせを実施。その後は、決められたスケジュールに沿ってホームヘルパーが訪問します。
これらの手続きは複雑に感じるかもしれませんが、ケアマネジャー(介護支援専門員)が丁寧にサポートしてくれるため、安心して進められます。
介護保険では足りない…その“困りごと”、小田急くらしサポートが解決します

「介護保険では頼めない、でも本当に助けてほしい…」。そんな声に応えるのが、自費サービスです。
小田急くらしサポートの訪問介護・生活サポートなら、介護保険のルールに縛られず、お客様一人ひとりの「ちょっとした困りごと」に柔軟に対応できます。
訪問介護生活サポート(自費介護サービス)は自費(全額自己負担)となりますが、その分制限なくさまざまなご要望に対応できるのが魅力です。
例えば、長時間の依頼や、通常の訪問介護サービスでは対応できない以下のようなご依頼も承ります。
- 一泊二日の旅行の付き添い
- 泊まり込みのご依頼
- イベントや外出時の終日付き添い
<小田急くらしサポートで対応可能なサービス例>
- 介護、介助のお手伝い
- 通院付添、院内介助
- 外出、余暇付き添い
- 日中、夜間見守り介護
- 生活支援
- 認知症ケア
- 障害者ケア
- 介護施設出張ケア など
介護保険内のホームヘルパーで外出の身支度を身体介護で頼み、自費介護サービスのホームヘルパーに外出の付き添いを頼み、散歩を楽しむといった組み合わせも可能です。
このように小田急くらしサポートの訪問介護生活サポート(自費介護サービス)と介護保険サービスと組み合わせることで、より安心で豊かな在宅生活を送れます。
サービスを組み合わせて最適な暮らしを
ホームヘルパーは「人」、訪問介護は「サービス」という違いがあり、訪問介護は介護保険を使った公的サービスのため利用にルールが存在します。
保険サービスで対応できない部分は「小田急くらしサポート」のような自費介護サービスで柔軟に補うことが可能です。両方を組み合わせることで、より充実した在宅生活が実現できるでしょう。
初めての介護は不安があって当然です。何より必要なのは、ご家族だけで抱え込まず、さまざまなサービスを上手に組み合わせること。小田急くらしサポートでは、介護に関するさまざまなお悩みのご相談を承っております。まずは、どのようなことでお困りかをお聞かせください。