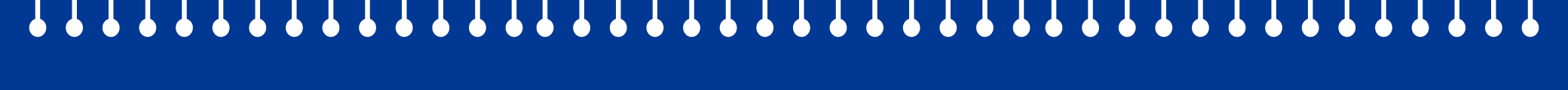
コウモリ対策と予防法!撃退グッズの選び方や効果、手順までを解説
住宅に侵入したコウモリに悩んでいませんか?
コウモリは健康被害やフン害、異臭などさまざまな問題を引き起こします。
本記事では、被害の実態からコウモリの特徴、効果的な追い出し方法、適切な時期や時間帯まで徹底解説します。自分でできる対策から専門業者への依頼が必要なケースまで、状況別に最適な対処法をご紹介!
100均グッズを使った対策から本格的な対策まで、コストと効果のバランスを考えた解決策をまとめています。ぜひ参考にしてくださいね。
目次
コウモリの被害とリスク
住宅に侵入したコウモリは、見た目の不気味さだけでなく、実際にさまざまな被害をもたらします。放置すればするほど問題は深刻化していくため、早めの対策が有効です。
| 被害 | 影響 | リスク |
|---|---|---|
| フン害 | 黒い米粒状のフンの蓄積強い悪臭の発生屋根裏木材の腐食天井のシミ雨漏りの原因 | 駆除・修繕費用がかかる |
| 健康リスク | 狂犬病やヒストプラスマ症などの媒介フンのカビによる呼吸器疾患アレルギー症状の誘発 | 特に子ども・高齢者に危険 |
| 被害の拡大 | 年1回、2〜3匹の繁殖1年で10匹以上に増加フン量の増加異臭・騒音の悪化 | 放置するほど対処が困難に |
被害を放置すると建物の劣化だけでなく、健康被害も深刻化し、対策費用も高額になります。コウモリのフンには病原体が含まれている可能性があり、特に免疫力の低い子どもや高齢者は注意が必要です。
コウモリ対策に最適な時期と時間帯
コウモリ対策には最適な時期と時間帯があります。
季節によって効果的な対策方法が異なりますので、それぞれの特徴を理解して効率的に駆除を行いましょう。
季節別のコウモリ対策の効果
コウモリ対策に最適な時期は春と秋です。それぞれの季節での効果的な対策方法を見ていきましょう。
- 春(4〜6月):冬眠明けで活動が活発な時期。忌避剤の効果が高く、軒下にテグスを張る、ハッカ油スプレーを散布する、超音波装置を設置するといった対策が効果的です。
- 秋(9〜10月):冬眠前で移動しやすい時期。春と同様の対策に加えて、侵入口を特定して塞ぐ作業も有効です。この時期に追い出すと再侵入しにくくなります。
時期によって行動パターンが異なるため、コウモリの行動に合わせた対策が効果的です。
効果的な対策のタイミング
コウモリは日没後30分〜2時間が最も活発に飛び回ります。この時間帯に観察すると、コウモリの出入りする場所を特定しやすくなります。
対策のベストタイミングは、巣から出た直後(19:00〜20:00頃)に忌避剤を散布すること。コウモリが外出中に忌避剤を設置することで、帰巣時の侵入を防ぐことができます。
ただし朝方(4:00〜5:00頃)に侵入口を塞ぐ作業は避けた方が良いでしょう。巣にいるコウモリが中に閉じ込められてしまうため、死骸や悪臭の原因になります。必ず完全に出払ったことを確認してから塞ぎ作業を行ってくださいね。
避けるべき時期
夏(7〜8月)と冬(11〜3月)はコウモリ対策に適していません。
夏は子育て期で、親だけを追い出すと子どもが取り残されて死に、悪臭や害虫発生の原因となります。この時期に対策をするなら、親子全てが出払ったことを確認してから行う必要があります。
冬は冬眠中で動きが鈍く、忌避剤への反応が弱くなります。対策の効果が低く、無駄な労力やコストがかかるため避けましょう。どうしても必要な場合は専門業者に相談することをおすすめします。
コウモリ対策で欠かせない侵入経路の特定
効果的なコウモリ対策のためには、まずコウモリがどこから侵入しているのかを特定することが重要です。
住宅のどこに注目すべきか、そしてコウモリの存在をどう見分けるかを解説します。
住宅の注意ポイント
コウモリはわずか1cmの隙間からでも侵入できます。主な侵入ポイントを確認しましょう。
<住宅の中でも特に注意すべき侵入ポイント>
- 瓦屋根の隙間:棟瓦の下や瓦のズレ部分
- 軒下の破損部分:板の腐食や隙間、金具の緩み箇所
- 換気口:直径10cm程度の開口部
- サイディングの隙間:経年劣化で浮きがある箇所
- エアコン配管周り:壁貫通部の隙間
- 雨樋の取り付け部分:壁との接合部
- 屋根と壁の接合部:構造上の隙間
特に古い家屋やリフォームを行った箇所は要注意です。
コウモリの存在を見分けるサイン
コウモリが住みついているかどうかを判断するポイントは、以下のとおりです。
| 状態 | 特徴 |
|---|---|
| フン | 黒く細長い米粒状(5〜8mm)で、触るとパサパサと崩れる。壁や地面に散らばっていることが多く、数が多いほど生息期間が長い可能性あり。 |
| 泣き声 | 夕方や明け方に「チチチ」という高い鳴き声がする。特に繁殖期は活発。 |
| 壁のシミ | 侵入口付近の壁に黒っぽいシミがある場合、コウモリの体が擦れた痕跡の可能性あり。 |
| 日中の異常音 | 屋根裏や壁の中から日中にカサカサという音がする場合、コウモリが潜んでいる可能性あり。 |
特にフンの量が増えている場合は、コウモリの数が増加している証拠なので、早急な対応が求められます。
自分でできるコウモリ対策の種類と効果
大きな被害になる前であれば、自分で対策することも可能です。コウモリ対策の種類や効果、特徴を紹介します。
忌避剤の種類と効果
忌避剤はコウモリが嫌う成分を利用して追い出す方法です。主にスプレータイプとジェルタイプがあります。
| 比較項目 | スプレータイプ | ジェルタイプ |
|---|---|---|
| 効果期間 | 即効性あり(数時間~1日程度) | 長期間(1~3カ月) |
| 特徴 | 広範囲に散布可能 | 設置型で手軽 |
| 価格帯 | 1,000~2,000円程度 | 2,000~4,000円程度 |
| デメリット | こまめな散布が必要 | 効果範囲が狭い |
| その他 | ハッカ油成分が多いほうが効果的 | ナフタレン系はニオイが強い(室内使用に注意) |
侵入口を特定してその周辺に集中的に使用することで、効率よくコウモリを追い出せます。
超音波装置の効果
超音波装置は人やペットには聞こえない高周波でコウモリを撃退する機器です。
- 電源式で設置が簡単(価格は2,000〜5,000円程度)
- 効果範囲は20〜50㎡程度
- 壁や家具で遮られるため、複数設置がおすすめ
- コウモリが慣れてくる(2〜3週間後)ため、定期的に設置場所や周波数を変えるのが効果的
超音波装置は初期の小規模な被害に対して効果的ですが、長期間放置された大規模な被害には効果が限られます。定期的に周波数を変えたり、他の対策と併用したりするのがおすすめです。
簡易対策
コウモリ対策は、身近な材料で手軽にできる簡易的なものもあります。
| 材料 | 効果 | 方法 |
|---|---|---|
| テグス | コウモリはエコーロケーション(反響定位)で糸を感知して避けるため、侵入を防げる | 釣り糸や園芸用の透明な糸を10〜15cm間隔で格子状に張る100均一やホームセンターで購入可能 |
| 蚊取り線香 | 煙がコウモリの呼吸を妨げるため嫌がる | 屋根裏に2〜3個置くと効果的火災リスクがあるため、安全な場所に設置する |
| LEDライト | コウモリは明るい光を嫌う | 侵入口付近に設置センサー式のものが便利で、夜間のみ点灯させることが可能 |
| アルミホイル | 反射光と風で揺れる音でコウモリを驚かせる | 軒下に吊るすと効果的手軽に試せるが、効果は限定的 |
これらの簡易対策は手軽に試せますが、効果は一時的なことが多いため、恒久的な解決を望む場合は他の対策と組み合わせましょう。
各対策のメリット・デメリットと費用相場
コウモリ対策の各方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
| 対策方法 | メリット | デメリット | 費用相場 |
|---|---|---|---|
| 忌避剤スプレー | ◎即効性がある◎使いやすい | ×持続性が低い×定期的な散布が必要 | 1,000〜2,000円程度 |
| 忌避剤ジェル | ◎持続性が高い◎設置が簡単 | ×効果範囲が限られる×臭いが強いものがある | 2,000〜4,000円程度 |
| 超音波装置 | ◎設置が簡単◎人やペットに害がない | ×コウモリが慣れる可能性あり×障害物で効果が減少 | 2,000〜5,000円程度 |
| テグス | ◎費用が安い◎視覚的に目立たない | ×設置に手間がかかる×劣化するため定期的な張替えが必要 | 500〜1,000円程度 |
| 蚊取り線香 | ◎すぐに準備できる◎費用が安い | ×火災リスクがある×効果時間が短い | 300〜500円程度 |
| プロの駆除 | ◎確実性が高い◎健康リスクを軽減 | ×費用が高い×日程調整が必要 | 10,000〜50,000円程度 |
対策方法の選択基準としては、被害の規模、住宅の構造、予算、自分の技術力などを考慮しましょう。
一時的な対策よりも恒久的な対策(侵入口の塞ぎなど)を行うことで、長期的な費用対効果は高くなります。何度も対策を繰り返すよりも、一度しっかりと対策することで再発を防げます。
効果的なコウモリの追い出し手順
コウモリを効果的に追い出すためには、正しい手順と安全への配慮が必要です。
ここでは安全に作業するための準備から具体的な追い出し手順、忌避剤の効果的な使用方法までを解説します。
安全に行うための準備と注意点
コウモリのフンには病原菌が含まれている可能性があるため、作業前に安全対策を万全にしましょう。
<必要な装備>
- マスク
- ゴーグル
- 長袖長ズボン
- 手袋
- 頭を覆うキャップ
<作業時の注意点>
- コウモリに直接触れない
- フンを吸い込まないよう注意する
- 暗所では十分な照明を用意する
- 高所作業は安定した足場で行う
- アレルギーや呼吸器疾患のある人は作業を避け、専門業者に依頼する
安全装備なしで作業すると健康被害のリスクが高まります。特に免疫力の低い人や子どもは作業を避け、安全を最優先にしましょう。
追い出し手順
コウモリを安全かつ効果的に追い出すための手順は以下の通りです
- 生息場所の特定:夕方の観察でコウモリの出入りする場所を確認
- 昼間に忌避剤を準備:スプレーかジェルを侵入口近くに配置
- 夕方〜夜のコウモリ外出確認:全てのコウモリが出て行ったことを確認
- 忌避剤の使用:侵入口周辺と内部に忌避剤を散布・設置
- 2〜3日観察:コウモリの出入りがないことを確認
- 侵入口を塞ぐ:コウモリがいないことを確認したら、金網や専用ネット、補修材で完全に塞ぐ
特に大事なのは、全てのコウモリが出て行ったことを確認してから侵入口を塞ぐことです。中にコウモリが閉じ込められると死骸の腐敗による悪臭や害虫の発生につながります。
忌避剤の効果的な使用方法
忌避剤を最大限に活用するためのポイントは、以下のとおりです。
| 種類 | 使用ポイント |
|---|---|
| スプレータイプ | 侵入口から50cm程離れた位置から散布する周囲30〜50cm範囲に満遍なく噴霧する風上から風下に向けて散布する屋内側にも同様に散布する効果は一時的なので、必要に応じて追加散布する |
| ジェルタイプ | 侵入口の両サイド(内外)に設置する吊り下げ型は天井から30〜50cm下げる熱源の近くには設置しない効果が持続する期間を考慮し、計画的に設置する |
<注意点>
- 人やペットが頻繁に通る場所への使用は控える
- 効果が弱まったら追加散布する
- 使用前に製品の注意書きをよく読む
忌避剤は正しく使用すれば効果的ですが、使い方を間違えると効果が半減します。説明書の指示に従いながら、コウモリの行動パターンを考慮した使用を心がけましょう。
プロに依頼した方がよいケース
コウモリ対策は被害の規模や状況によって、自力で行うべきか専門業者に依頼すべきかが変わってきます。
小規模な被害(1〜2匹程度)であれば、忌避剤の使用と侵入口の塞ぎによる自力対策で十分対応可能です。一方、コウモリの数が増えると対策の難易度も上がります。
<自力対策とプロ依頼の判断基準>
| 被害の規模 | 状況 | 対応 | プロの必要性 |
|---|---|---|---|
| 小規模(1〜2匹) | フンが少量侵入口が1か所低所で作業可能 | 忌避剤の使用侵入口の塞ぎ | 低い |
| 中規模(3〜5匹) | フンが複数箇所侵入口が2〜3か所 | 忌避剤の使用専門的な防獣ネット設置 | 中程度 |
| 大規模(6匹以上) | フンが大量複数の侵入口作業が危険 | 巣の完全除去と消毒複数侵入口の特定・封鎖 | 高い |
特に以下のような状況では、業者への依頼を強くおすすめします。
- 高所作業が必要:屋根や2階以上の高所は素人の作業では危険です
- 自力対策を試しても効果がない:何度も対策しても再発する場合
- 過去に再発している:一度は追い出せても繰り返し戻ってくる場合
- 建物に構造的な問題がある:老朽化や建物の複雑な構造で隙間が多い場合
プロの業者は、特殊カメラでの巣の特定や、一方通行ドア(エクスクルーダー)の設置など、専門的な技術と道具を用いて確実に対策を行います。適切な消毒も行われるため、健康リスクの軽減にもつながります。
自分の安全と確実な対策を考えると、中〜大規模の被害や複雑な状況ではプロに依頼することが結果的にコスト面でも有利になることが多いです。
コウモリ駆除の料金相場と業者選び
プロに依頼する場合の費用相場と、信頼できる業者を選ぶためのポイントを紹介します。
駆除作業の料金相場
コウモリ駆除の一般的な料金相場は10,000円〜です。この費用は、以下のような内訳で構成されています。
- 調査診断費:3,000円~
- 駆除・追い出し作業:5,000円~
- 侵入口封鎖:5,000円〜
- 消毒作業:3,000円~
料金に影響する主な要因としては、コウモリの数、侵入口の数と場所、建物の構造、作業の難易度、地域差などが挙げられます。また、追加オプションとして保証サービス(6ヶ月〜1年)が付く場合は5,000円〜上乗せされることが一般的です。
見積もりの際には内訳を明確にしてもらい、どのような作業が含まれているのかを確認しましょう。追加料金が発生する可能性がある場合は、事前に説明を受けておくことも大切です。
業者選びで確認すべきポイント
信頼できるコウモリ駆除業者を選ぶためのポイントは以下の通りです。
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 技術面 | コウモリ専門の知識を持っているか建物構造への理解があるか適切な消毒技術を持っているか |
| 実績 | 施工実績数は十分か成功事例の写真などが提示できるか顧客の評価・口コミはどうか |
| 対応 | 無料現地調査をしてくれるか詳細な見積書を提示してくれるか作業内容をわかりやすく説明してくれるか |
| アフターケア | 保証期間はあるか再発時の対応はどうなっているか定期点検サービスはあるか |
| 価格 | 極端に安い場合は要注意明確な料金体系になっているか追加料金の可能性について説明があるか |
| 資格 | 建築関連の資格や害獣駆除の専門資格を持っているか |
なお小田急暮らしサポートでは、信頼できる業者をご紹介しています。コウモリ対策でお困りの際は、ぜひご相談ください。
再発防止のための予防策
コウモリが一度住み着いた住宅は再発リスクが高いため、効果的な予防策を継続的に行うことが重要です。
住宅の定期点検と環境整備を組み合わせた総合的なアプローチで、コウモリの再侵入を防ぎましょう。
定期的な住宅チェックポイント
| 箇所 | チェックポイント | 頻度 |
|---|---|---|
| 屋根 | 瓦のズレや破損棟部分の隙間 | 春・秋の年2回 |
| 軒下 | 板の腐食や隙間金具の緩み | 春・秋の年2回 |
| 換気口 | ネットの破れフードの変形 | 四半期ごと |
| 外壁 | ひび割れや隙間サイディングの浮き | 春・秋の年2回 |
| 雨樋 | 取り付け部の隙間詰まり | 雨季前と秋 |
| 設備周り | アンテナ・エアコン配管の貫通部 | 年1回 |
特に雨や風の強い日の後は、被害が生じやすいので臨時点検をすることをおすすめします。点検時に小さな隙間や破損を見つけたら、その場で補修するか、専門業者に依頼しましょう。
コウモリを寄せ付けない環境づくり
コウモリが好まない環境を作ることも重要な予防策です。以下のような対策を組み合わせて行うとより効果的でしょう。
- 餌の昆虫を減らす:ハーブ(ミント、ラベンダー)を植える、LED電球やイエローランプに変更
- 定期的な予防対策:軒下や換気口周辺にハッカ油を春秋に散布、軒下にテグス格子を設置
- 侵入口の封鎖:コウモリ追い出し後、ステンレス製金網(5mm目以下)やコーキング材で隙間を完全に塞ぐ
- 換気口の保護:通気性を確保しながら防獣ネットカバーを設置
予防対策は単発ではなく継続的に行うことが効果的です。特に春と秋の定期点検を習慣にすることで、早期発見・早期対策につながります。
侵入口の封鎖後も1週間は様子を観察し、コウモリの再侵入がないことを確認しましょう。
コウモリ対策で快適な住環境を守ろう(まとめ)
コウモリ被害は早期発見・早期対策が重要です。初期段階であれば忌避剤やテグスなどの自力対策も効果的ですが、被害が拡大するほど対応は困難になります。
小規模被害(1〜2匹)は自力対策が可能ですが、中規模以上の被害や高所作業が必要な場合は安全面を考慮してプロへの依頼がおすすめです。特に健康リスクが心配な場合や建物への被害が深刻な場合、専門業者による確実な対策が最適な解決策となります。
なお小田急暮らしサポートでは、コウモリ対策を含む住まいのトラブルに関するサービスを提供しています。無料見積りも行っていますので、お気軽にご相談ください。






